転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- 【暮らし】<はたらく>労組をつくる 理論編 使用者との交渉 対等に
【暮らし】<はたらく>労組をつくる 理論編 使用者との交渉 対等に
2012/12/14
長引く景気低迷によるリストラや非正規雇用の拡大などで、労働組合の弱体化が指摘されて久しい。だが、賃上げなどを実現してきた労組の役割は本来、小さくはない。中小企業には労組がないところも多いが、実は自らつくることもできる。労組とはそもそも何か。理論編と実践編の2回に分け、手法を紹介する。(三浦耕喜)
東京都八王子市に住む男性(43)は、11月25日、勤務先の運送会社に労組支部の結成を伝えた。組合員は2人だけ。だが、今月七日に会社から団体交渉に応じる返事が来た。男性は「時間はかかるが、話し合う土台ができた」と話す。
労働運動は「万国の労働者よ、団結せよ」という言葉が源だ。しかし、裏返せば、この言葉は「団結しなければ、雇用主にはかなわない」という現実をも指摘している。
実際、非正規雇用が拡大し、賃下げやサービス残業などで正社員の待遇も劣化してきた近年の流れは、労組の組織率低下と軌を一にしている。労組がない会社も多い。雇用でトラブルに遭っても、1人で会社組織を相手に闘うのは困難だ。
そんなときは、労組をつくることができる。それを足掛かりに使用者と対等の立場で交渉することも、法律で保護される。
その根拠となるのが労働組合法だ。歴史的な背景もある。戦前に労働運動が弾圧されたことから、連合国軍総司令部(GHQ)が民主化の一環として進め、立法化された。
労組法第1条は「労働者が使用者との交渉で対等の立場に立つこと」を目的に掲げる。使用者とフェアな交渉ができるよう、同法は立場の弱い労働者を下支えする。
非正規雇用も含めた職場の労組づくりに取り組む「プレカリアートユニオン」の大平正巳委員長(43)は同法の利点をこう解説する。「労組をつくれば、使用者が拒否できない団体交渉権を獲得できる。さらに刑事・民事両面で免責を受けられる。また労働委員会への救済申し立てなどで保護が得られる」
労組が団体交渉を求めれば、使用者側は拒否できない。拒否できるのは「週に何回も団体交渉を求めるので業務に著しい支障を来す」など、よほどの事情のときだけだ。
大手牛丼チェーンの運営企業が「アルバイトは業務委託であって労働者ではない」との論理で団体交渉に応じなかった例があった。だが、東京都労働委員会も中央労働委員会も東京地裁も東京高裁も、団体交渉に応じるよう判断している。首都圏青年ユニオンの河添誠書記長(48)は「交渉を入り口から拒否すれば、企業としてあるまじき姿を社会に示すことになる」と話す。
では、労組をどうつくるか。自分も含め二人以上の仲間を集め、規約と役員を選出すれば結成できる。規約と役員は総会を開いて決定する。都道府県の労働委員会に争いを調停してもらうためには、地元の労働委員会への手続きが必要。団体交渉を始めたい場合は、使用者側に労組を結成したことを通告し、団体交渉を求める意思を示すことで足りる。
その場合は、労組の組合員名簿も使用者側に渡す。労組を結成したことで組合員に圧力をかけないよう、使用者側を抑えるためだ。組合員を狙い撃ちにした不利益が明らかになれば、不当労働行為として禁じられる。
大平氏は「職場に問題があっても、多少の解決金で処理され、結局、辞めざるを得ずに職を失うパターンは多い。働きながら労働条件をよくするためには、労組は重要な道具だ」と話している。
次回(21日に掲載予定)は実際に職場で労組をつくった例を報告する。
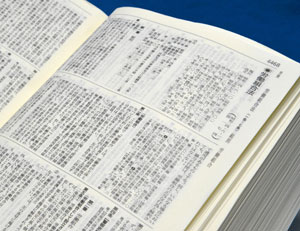
- 六法全書に記載されている労働組合法
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/10/10
- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」
- 2025/10/01
- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル
- 2025/09/25
- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申
- 2025/08/14
- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査
- 2025/08/13
- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人



