転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- 【暮らし】<はたらく>メンタル不調 早期対策で
【暮らし】<はたらく>メンタル不調 早期対策で
2011/01/01
従業員のうつ病対策など、企業のメンタルヘルスケアの取り組みが進んでいる。中でも注目されているのが、不調者の早期発見と治療、未然防止。先進的な実践例から制度のあり方を探った。 (竹上順子)
「電話でもメールでも携帯電話でも、相談を受けている。いつでも話せることが大切。二十四時間対応し、出られなかったときは必ずかけ直します」
生活設備機器メーカー「ノーリツ」(神戸市)の森下文昭・ライフプランサポート室長は、ストレスを抱えた社員への対応についてこう語る。話すことで気持ちや状況を整理でき、深刻な状況に陥る前に解決できる例も少なくないという。
メンタル不調者の早期発見のため同社が力を入れるのが、異動に伴うストレスのチェック。初任地への赴任や転勤、部下を持って一~二カ月後の社員に、三十項目の「ストレス状況チェックリスト」をメールで送付。十五項目以上に当てはまる“高ストレス”状態の場合、サポート室との面談か、産業医や地元の専門医への受診を呼び掛けている。
森下さんらサポート室のスタッフは、ほぼ全員が産業カウンセラーの資格を持つ。面談依頼があれば全国に飛び事業所以外の場所で会う。相談段階では会社側に伝えず、相談者とサポート室とでやりとりし、休職など調整が必要になったら、相談者が上司に伝える。
自己チェックは二〇〇六年にスタート。森下さんは「早期の受診が増えたり、長期休業者の数が二桁から一桁になるなど、効果は出ている」と話す。
◇
厚生労働省の〇七年労働者健康状況調査によると、メンタルヘルスケアに取り組む事業所の割合は約34%で、十年前に比べて約7ポイント増えた。
取り組みの効果に対しては、不調者の早期発見などいわゆる「二次予防」への期待が高いことが、日本生産性本部メンタル・ヘルス研究所(東京都渋谷区)の上場企業へのアンケート(有効回答数三百二十三社)から分かった=グラフ。
現在は労働安全衛生法で、一カ月の残業時間が百時間を超えるなどした場合、事業者は労働者の申し出に応じ、医師の面接指導などを行うことが義務付けられている。
さらに厚労相の諮問機関・労働政策審議会は昨年、同法改正に向けた建議で、すべての労働者のストレス状況を医師が確認し高ストレスの人の面接指導などを行う「新たな枠組み」の導入を提案した。
職場のメンタルヘルスに詳しい東京大大学院の川上憲人教授(精神保健疫学)は「二次予防よりも、不調者の発生を未然に防ぐ『一次予防』の方が、かけるコストに対する効果は高い」と話す。ストレスチェックの結果を個人への対応に生かすだけでなく、職場ごとの傾向を出して環境改善につなげれば、予防に加え、従業員の労働意欲も上がると指摘する。
◇
「富士ゼロックス」(同港区)は一九九四年から、産業医らが年一回、定期健康診断の結果を基に、約一万人の社員すべてとの「全員面談」を実施。山中俊治・健康推進センター長は「早期発見だけでなく、不調になった時に医師と会うことへの敷居を下げたり、本人の心身の健康への自覚を促したりする効果もある」と説明する。
問題が見つかった場合、産業医は人事部に対し、社員の処遇についての助言や、職場環境の問題点などを意見書で伝える。事業所によっては、自己催眠法でストレスを緩和する「自律訓練法」の教室を開くなど、セルフケアにも力を入れている。
川上教授は「チェック後に、ストレスと上手に付き合っていく対処法を教えるストレスマネジメント教育をしたり、個人情報の保護、結果によって従業員が不利益を被らないような仕組み作りも必要」と呼び掛けている。
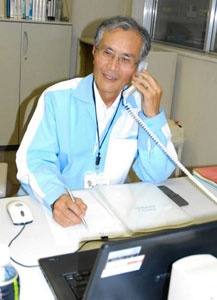
- ライフプランサポート室で電話を受けるノーリツの森下文昭室長=兵庫県明石市で
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/10/10
- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」
- 2025/10/01
- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル
- 2025/09/25
- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申
- 2025/08/14
- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査
- 2025/08/13
- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人


